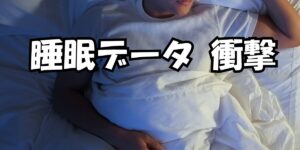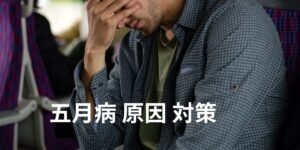先日、友人からお母様の認知症が進み、夜中に徘徊することが増えたという話を聞きました。
遠方に住んでいるわけではないのですが、やはり夜間は近くにいても気が付かないことが多く、心配で眠れない日々が続いたそうです。
そこで、スマホから様子を確認できる監視カメラを設置し、夜中に動きがあったときに通知が来るように設定して、少しだけ安心できるようになったと言っていました。
実は、私もいずれは離れて暮らす親のことが心配になってくるだろうと思っています。普段は元気でも、年齢を重ねると何が起こるか分かりませんし、本人も不安を抱えるかもしれません。
そこで「離れた場所からでも親を見守るにはどんなグッズやサービスがあるのだろう?」と改めて気になり、いろいろと調べてみることにしました。
離れた親の見守りグッズ スマホで確認できるカメラ
まず友人が導入したのが、いわゆる「スマホで確認できる見守りカメラ」です。Wi-Fiにつないでおけば、外出先からでも映像をリアルタイムで確認できるタイプが増えています。
- 夜間の暗所対応:暗い部屋でも赤外線モードで人の動きを映し出してくれる製品が多い。
- 動体検知・通知機能:人が動いたりするとスマホに通知が送られる機能が便利。
- 双方向音声:こちらの声掛けができたり、向こうの声を拾ったりできる機能もある。
ただ、カメラを設置するときにはプライバシーの問題もあるので、親御さん本人との話し合いは大切です。
「監視されている」と感じさせないような配慮や、一部の部屋だけにするなど、目的や設置場所をきちんと説明して理解を得ることが望ましいですね。
センサーや通知デバイス
カメラ以外にも、家のドアや窓にセンサーを取り付けることで、開閉があったときにスマホに通知が送られるタイプの見守りグッズがあります。夜中に外出してしまった場合など、気付くきっかけになるので、認知症の徘徊対策に利用される方も多いようです。
- ドア開閉センサー:人の出入りがあったらスマホへ通知。
- 人感センサー:部屋の出入りや廊下の往来を検知して通知。
- ベッドセンサー:寝ているはずの時間に離床してしまうと通知が届く仕組み。
また、ガスや火の元を心配する場合は、火災報知器と連動したアラートやコンロの見守り機能があるサービスもあります。これらの機能がついていれば、離れた場所からでもトラブルにいち早く気づけるので安心です。
ウェアラブル・GPS端末
さらに、外出時や徘徊対策として、GPS端末やGPS機能付きのウェアラブルデバイスを持ってもらう方法もあります。
- GPSポーチ・キーホルダータイプ:かばんに入れておいたり、家の鍵と一緒につけておけば、万が一行方が分からなくなったときに捜索が比較的容易。
- 腕時計型デバイス:常時身につけていられるので、持ち歩きを忘れるリスクが減らせる。緊急連絡ボタン付きの製品もある。
認知症の症状がある場合は、本人にデバイスを持ってもらうことに抵抗感があったり、使い方が難しく感じられてしまうこともあるので、購入前に実際の操作性や装着感などを確かめるのが良いでしょう。

見守りサービス・SNSコミュニティ
グッズだけでなく、企業が提供する見守りサービスを利用するのも手段のひとつです。
- 地域の見守りネットワーク:自治体やNPOが協力して、徘徊などの問題が発生した場合、近隣住民にも捜索を呼びかけるシステム。
- 介護サービスとの連携:訪問介護やデイサービスなどのスタッフとのやり取りを円滑に行うことで、普段の生活状況を共有できる場合もあります。
- オンラインコミュニティ:同じ悩みを持つ人同士が情報を交換できる場が多く、実際に使ってみたグッズの感想やトラブルシューティングなどを知ることができる。
費用や継続性も考慮しよう
こういった見守りグッズやサービスは、初期費用が高額になったり、月々の維持費がかかったりするものもあります。また、テクノロジーに不慣れな親御さんの場合は、慣れていただくまで根気よくサポートし続ける必要があります。
- 導入費用の確認:本体価格だけでなく、クラウド録画のサブスクリプションなど追加料金が必要かどうか。
- メンテナンスやサポート:機器が故障した際のサポート体制や修理費用もチェック。
- 本人への負担:カメラの設置やデバイスの装着が心理的・身体的に負担にならないか、日常的に操作できるかどうか。

まとめ
離れて暮らす親の見守りは、私たち世代にとっても他人事ではありません。特に認知症の症状が進むと、本人を危険から守るためにも、早めに対策を検討することが重要だと感じています。友人の体験をきっかけに、改めてさまざまなグッズやサービスを調べる中で、技術の進歩によって以前より手軽に導入しやすい商品が増えている一方、プライバシーやコスト面などの課題があるのも事実です。
大切なのは、親御さん本人ときちんと話し合い、「どこまで見守るのか」「どのようなトラブルを想定して、どんなグッズを使うのか」を家族が納得したうえで決めること。安心かつ快適に日々を過ごせるよう、一度じっくりと検討してみませんか?
私自身も、これからますます離れた両親への見守りについて勉強していこうと思っています。もし同じように悩んでいる方がいたら、一緒に情報を集めて、より良い方法を見つけていきましょう。